一時期、自己啓発の本にはまっていた私は、最近スピリチュアルなことにも興味をもっている。それでもっともお気に入りなのが「月」に関すること。なかでも新月パワーをちょっと信じている。
この新月パワーというのは、新月の時期に願い事をしたり、物事をスタートさせると月が満ちていくように、スムーズに実現へ向かうという考え方だ。とくに自然体でいればいいようなので、その点をいたく気に入っている。
詳しく書かれた本もあるので興味がある方は、こちらを読んでみて。
そして「The moon age calendar」というサイトも発見した。きれいなデザインで見ているだけで癒される〜。このサイトは月齢や月に関することが載っていて、とくにタイムリーな月齢を知れるのが大きな魅力かな。
最近買ったアイシャドーも「ルナソル(Lunasol)」。Luna(月)sol(太陽)という意味なので、何かと縁を感じております。
この新月パワーというのは、新月の時期に願い事をしたり、物事をスタートさせると月が満ちていくように、スムーズに実現へ向かうという考え方だ。とくに自然体でいればいいようなので、その点をいたく気に入っている。
詳しく書かれた本もあるので興味がある方は、こちらを読んでみて。
そして「The moon age calendar」というサイトも発見した。きれいなデザインで見ているだけで癒される〜。このサイトは月齢や月に関することが載っていて、とくにタイムリーな月齢を知れるのが大きな魅力かな。
最近買ったアイシャドーも「ルナソル(Lunasol)」。Luna(月)sol(太陽)という意味なので、何かと縁を感じております。
PR
すっごく面白かった〜。という本を久しぶりに紹介します。
村上龍さんの著作『半島を出よ』(幻冬舎発行)です。
書店で見て気になってはいたのだけど、上下巻あるし、どうしよーと思ってなかなか購入には至らなかった本。でもお仕事でご一緒させていただいているKさんが「面白すぎて新幹線内で読破した」というのを聞き、私も! と読み始める。
北朝鮮の反乱軍に福岡県を乗っ取られてしまう話で、読む前は「どんな茶番になっちゃうんだろう」って心配していたけど、これがびっくり超リアル。これ将軍さま読んだら、きっとやっちゃうよ。「Youやっちゃいな」って感じで。
それでまた、日本政府の対応ったらぐだぐだで、これまた超リアル。みんな忙しいふりしているんだけど、大切なことは何も決められてないじゃん! みたいな。よくテレビで見る光景だけど、非常事態までそうなの!? とまぁ、現実っぽいのです。
私は龍さんのこと、もう小説には興味ないのかなって勝手に思っていたけど(いろいろ手広くって)、こんなに面白すぎる物語を書いてくださるなら、もっとお願いします! と、声を大にして言いたい。
とにかく、ダーッとのめり込んで読める本をお探しの方におすすめします。
村上龍さんの著作『半島を出よ』(幻冬舎発行)です。
書店で見て気になってはいたのだけど、上下巻あるし、どうしよーと思ってなかなか購入には至らなかった本。でもお仕事でご一緒させていただいているKさんが「面白すぎて新幹線内で読破した」というのを聞き、私も! と読み始める。
北朝鮮の反乱軍に福岡県を乗っ取られてしまう話で、読む前は「どんな茶番になっちゃうんだろう」って心配していたけど、これがびっくり超リアル。これ将軍さま読んだら、きっとやっちゃうよ。「Youやっちゃいな」って感じで。
それでまた、日本政府の対応ったらぐだぐだで、これまた超リアル。みんな忙しいふりしているんだけど、大切なことは何も決められてないじゃん! みたいな。よくテレビで見る光景だけど、非常事態までそうなの!? とまぁ、現実っぽいのです。
私は龍さんのこと、もう小説には興味ないのかなって勝手に思っていたけど(いろいろ手広くって)、こんなに面白すぎる物語を書いてくださるなら、もっとお願いします! と、声を大にして言いたい。
とにかく、ダーッとのめり込んで読める本をお探しの方におすすめします。
今日はウェブでこんな記事を見つけた。
「新宿西口バス放火事件」
(「無限回廊」のトップページから探してください!)
慣れ親しんだ新宿に、そんな事件があったかなぁと思い、ふとクリックしてみたのだが、これは1980年に起こった昔の事件だった。そういえばなんとなく聞いたことがあるような気がする。
記事を読んで、なぜだかわからないが涙が出てきた。
こうした犯罪は起きてはならないのだが、生み出している社会があるというのも現実にある。責任の所在がなんだかループしてしまうようで、なんだか心がモヤモヤしてしまう事件は、高村薫さんの小説『レディジョーカー』(毎日新聞社発行)を思い出してしまった。
言わずと知れた「グリコ・森永事件」を題材にした超大作。ミステリーという枠をはるかに越える社会派小説だ。この小説の登場人物の背景も、それぞれに闇というよりも濃いグレーな部分を持っている。事件の展開も面白いが同時にとても考えさせられる小説だった。
こうした考えさせられる事件というのは、ある意味で解決することができる可能性を持っているような気がする。ほんのわずかでも希望がありそうな。でも最近は、池田小学校の児童殺傷事件のように、思考停止してしまうような事件が増えていて、時折本当に不安になってくる。
「新宿西口バス放火事件」
(「無限回廊」のトップページから探してください!)
慣れ親しんだ新宿に、そんな事件があったかなぁと思い、ふとクリックしてみたのだが、これは1980年に起こった昔の事件だった。そういえばなんとなく聞いたことがあるような気がする。
記事を読んで、なぜだかわからないが涙が出てきた。
こうした犯罪は起きてはならないのだが、生み出している社会があるというのも現実にある。責任の所在がなんだかループしてしまうようで、なんだか心がモヤモヤしてしまう事件は、高村薫さんの小説『レディジョーカー』(毎日新聞社発行)を思い出してしまった。
言わずと知れた「グリコ・森永事件」を題材にした超大作。ミステリーという枠をはるかに越える社会派小説だ。この小説の登場人物の背景も、それぞれに闇というよりも濃いグレーな部分を持っている。事件の展開も面白いが同時にとても考えさせられる小説だった。
こうした考えさせられる事件というのは、ある意味で解決することができる可能性を持っているような気がする。ほんのわずかでも希望がありそうな。でも最近は、池田小学校の児童殺傷事件のように、思考停止してしまうような事件が増えていて、時折本当に不安になってくる。
今日、『桃仙』(牛女舎発行)が届いた。
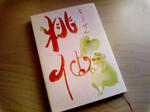
これは私のはんこをつくってくれた山本桃仙さんが書いた初エッセイ。なぜ、はんこ屋さんがエッセイ?と不思議に思う人もいるかもしれないが、この山本桃仙さんは知る人ぞ知る(って、いかにもな表現だけど)、世田谷区池尻にある山本印店の店主。ビジネスマンやOL、主婦にはもちろんのこと、政界、財界の方や芸能人など著名人も多く訪れるというはんこ屋さんなのだ。
使っているはんこを持っていくと、それを見ながらさまざまなアドバイスをしてくれて、必要ならばはんこをつくってくれる。このはんこがまた可愛い♪
クチコミだけでなく最近ではブログ上でも良く目にするので、久しぶりに「はんこ屋さん元気かな〜」と思ってチェックしていたら、なんといつの間にかホームページを作成していた。おぉ、近代化。ちょっとビックリ。さらにエッセイまで販売していたので、つい購入してしまった。
この本には、桃仙さんのはんこに対する考えやその不思議な鑑定眼の話が書かれていて、すごく興味深く読むことができた。この世界はとってもシンプルだと私は思っている。それに対するヒントをもらったような気がした。読み終わった後は、なんだか心がほんわかするので、桃仙さんのはんこを持っている人もそうでない人もオススメの本だと思う。
私がはんこ屋さんに伺った時の話は、また今度しますね。お楽しみに。
これは私のはんこをつくってくれた山本桃仙さんが書いた初エッセイ。なぜ、はんこ屋さんがエッセイ?と不思議に思う人もいるかもしれないが、この山本桃仙さんは知る人ぞ知る(って、いかにもな表現だけど)、世田谷区池尻にある山本印店の店主。ビジネスマンやOL、主婦にはもちろんのこと、政界、財界の方や芸能人など著名人も多く訪れるというはんこ屋さんなのだ。
使っているはんこを持っていくと、それを見ながらさまざまなアドバイスをしてくれて、必要ならばはんこをつくってくれる。このはんこがまた可愛い♪
クチコミだけでなく最近ではブログ上でも良く目にするので、久しぶりに「はんこ屋さん元気かな〜」と思ってチェックしていたら、なんといつの間にかホームページを作成していた。おぉ、近代化。ちょっとビックリ。さらにエッセイまで販売していたので、つい購入してしまった。
この本には、桃仙さんのはんこに対する考えやその不思議な鑑定眼の話が書かれていて、すごく興味深く読むことができた。この世界はとってもシンプルだと私は思っている。それに対するヒントをもらったような気がした。読み終わった後は、なんだか心がほんわかするので、桃仙さんのはんこを持っている人もそうでない人もオススメの本だと思う。
私がはんこ屋さんに伺った時の話は、また今度しますね。お楽しみに。
先週のブログ活動は、たった1日でした…。「ブックマークに入れたのでがんばってください」というお声もいただいたので、ご期待に応えていきたいと思います!でも書くのは結構楽しいので、毎回ルンルンなのです♪
ところで、「言葉」や「本」など、ちょっと文化的な香りのするところをテーマにしたいと思っていたこのブログ。(そういえば、ね)今回はおすすめ本を思いついたので、それを紹介することにする。
デュラン・れい子さん著の『一度も植民地になったことがない日本』(講談社発行)という新書だ。
以前にも戦争で侵略されたことがないのは、日本とタイぐらいだと聞いたことがあったが、植民地という視点の話は耳にしたことがなかったので、「ほぉ!」と興味津々で手に取ってみた(そういえば同じようなことなんだけど)。
著者のデュラン・れい子さんは、博報堂で初の女性コピーライターとして活躍後、スウェーデン人と結婚して、海外に在住しているという方。彼女が言うには、なんでもヨーロッパではよく知られていることのようで、改めてそうした視点に立ってみると、日本という国のユニークさが見えてくるというのだ。
本によると、日本では宣教師を弾圧したり、鎖国があったために植民地になることなく、独自の文化を残すことができたという話も出てくる。
宣教師って、ある意味支配するために送り出された人たちだったんだ〜。私はてっきり、ただのいい人たちなのかと思っていた。鎖国にしても、なにもそんなに闇雲に拒まなくても〜って思っていたけど、先人たちにはいろいろなお考えがあったのね。
でもまわりを寄せつけなかったことで、「黄金の国、じぱんぐ」とか言われて、ブランド価値を高めたのは成功なのかも。
こうして客観的に日本を見ていくと、当時はかなりキワい国だったのではないかと思う。開国後、国内でしばらくバタバタもめてから、今度は外に目がいくようになり戦争の時代になっていくでしょ? 世界の流れには逆らえなかったのかも知れないけど、結構強引な感じで押し進めていった。すっごく小さな国なのにね。
戦争に負けたら負けたで、アメリカさんに食料を恵んでもらって、やっと元気になり始めたら、また突き進む。あっという間に高度成長期に沸き上がる。そして今度は経済で存在感を示し、先進国の仲間入りを果たす。スゴイ…
もしかして、日本というのが1人のキャラクターになっていたら、私は間違いなく好きになっちゃうなぁ〜。(本の内容とはちょっと脱線しちゃったけど)そんなことを考えさせてくれる、興味深い本でした。
ところで、「言葉」や「本」など、ちょっと文化的な香りのするところをテーマにしたいと思っていたこのブログ。(そういえば、ね)今回はおすすめ本を思いついたので、それを紹介することにする。
デュラン・れい子さん著の『一度も植民地になったことがない日本』(講談社発行)という新書だ。
以前にも戦争で侵略されたことがないのは、日本とタイぐらいだと聞いたことがあったが、植民地という視点の話は耳にしたことがなかったので、「ほぉ!」と興味津々で手に取ってみた(そういえば同じようなことなんだけど)。
著者のデュラン・れい子さんは、博報堂で初の女性コピーライターとして活躍後、スウェーデン人と結婚して、海外に在住しているという方。彼女が言うには、なんでもヨーロッパではよく知られていることのようで、改めてそうした視点に立ってみると、日本という国のユニークさが見えてくるというのだ。
本によると、日本では宣教師を弾圧したり、鎖国があったために植民地になることなく、独自の文化を残すことができたという話も出てくる。
宣教師って、ある意味支配するために送り出された人たちだったんだ〜。私はてっきり、ただのいい人たちなのかと思っていた。鎖国にしても、なにもそんなに闇雲に拒まなくても〜って思っていたけど、先人たちにはいろいろなお考えがあったのね。
でもまわりを寄せつけなかったことで、「黄金の国、じぱんぐ」とか言われて、ブランド価値を高めたのは成功なのかも。
こうして客観的に日本を見ていくと、当時はかなりキワい国だったのではないかと思う。開国後、国内でしばらくバタバタもめてから、今度は外に目がいくようになり戦争の時代になっていくでしょ? 世界の流れには逆らえなかったのかも知れないけど、結構強引な感じで押し進めていった。すっごく小さな国なのにね。
戦争に負けたら負けたで、アメリカさんに食料を恵んでもらって、やっと元気になり始めたら、また突き進む。あっという間に高度成長期に沸き上がる。そして今度は経済で存在感を示し、先進国の仲間入りを果たす。スゴイ…
もしかして、日本というのが1人のキャラクターになっていたら、私は間違いなく好きになっちゃうなぁ〜。(本の内容とはちょっと脱線しちゃったけど)そんなことを考えさせてくれる、興味深い本でした。

![[魂の願い]新月のソウルメイキング](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51RKV7XVXZL._SL160_.jpg)









